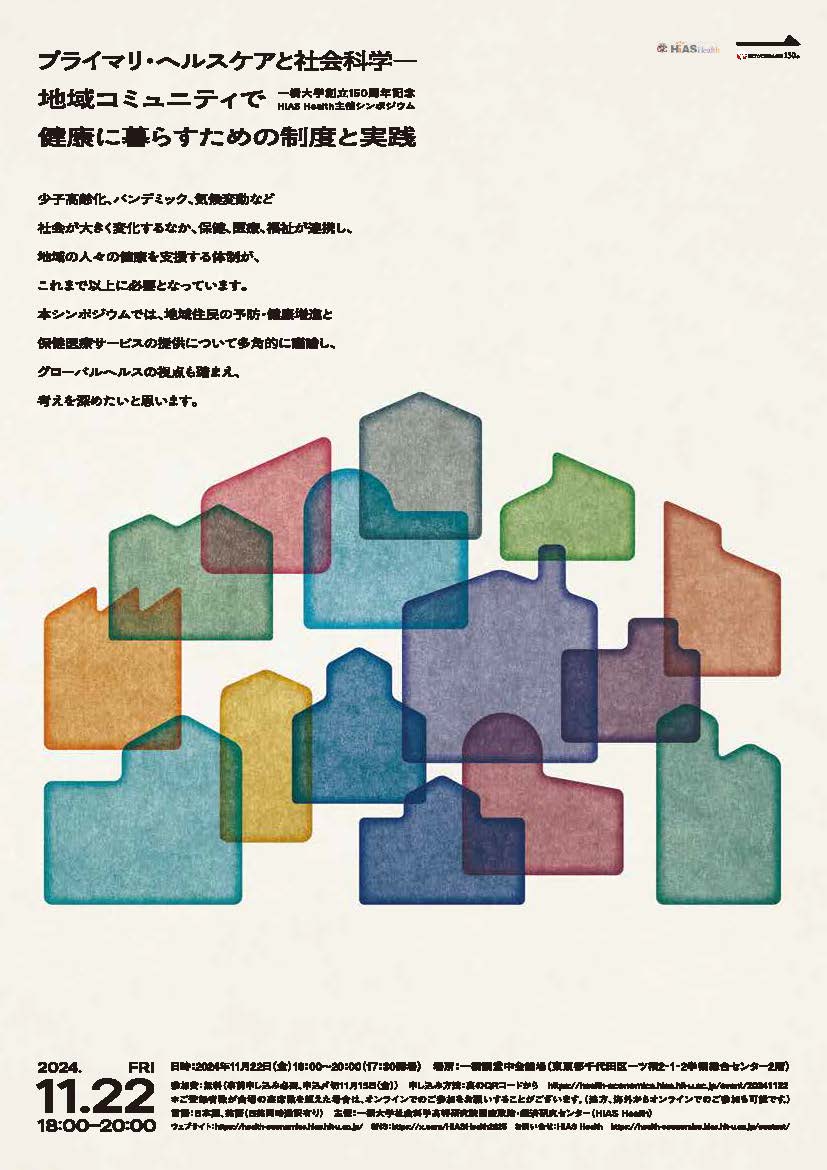お知らせ
「日本経済新聞」掲載のお知らせ
- お知らせ

医療法人社団悠翔会理事長の佐々木淳が登壇させていただいた、2024年11月22日開催の一橋大学創立150周年記念HIAS Health主催シンポジウム・政策フォーラム「プライマリ・ヘルスケアと社会科学ー地域コミュニティで健康に暮らすための制度と実践」(https://health-economics.hias.hit-u.ac.jp/event/20241122/)の様子が、2024年12月24日付けの日本経済新聞・夕刊にて紹介されました。
少子高齢化、パンデミック、気候変動など社会が大きく変化するなか、保健、医療、福祉が連携し、地域の人々の健康を支援する体制がこれまで以上に必要になっています。第1部「日本のヘルスシステムと地域医療」では、井伊雅子氏(一橋大学大学院経済学研究科/国際・公共政策大学院教授)が日本の地域医療とヘルスリテラシーについて、小塩隆士氏(一橋大学経済研究所特任教授、中央社会保険医療協議会会長)が地域医療と診療報酬について講演され、佐々木は「在宅医療:地域コミュニティのステークホルダーとの協働」をテーマに、訪問看護や歯科との連携についてお話しさせていただきました。
第2部「グローバルヘルスとプライマリ・ヘルスケア」では、Kara Hanson氏(ロンドン大学衛生熱帯医学大学院公衆衛生政策学部教授、国際医療経済学会会長)が地域医療と財政についてお話しされました。第3部では、行政、財政、社会保障の専門家である林修一郎氏(厚生労働省保険局医療課課長)、佐藤主光氏(一橋大学大学院経済学研究科教授)、山重慎二氏(一橋大学大学院経済学研究科/国際・公共政策大学院教授)のコメントに続き、第1・2部の講師が加わり、過疎地の医療サービス、医療の質、プライマリ・ヘルスケアの公的資金投入などについてディスカッションを行いました。
医療の質を評価する際には評価軸が問題になります。佐々木は、「国民が医療サービスに求めるもの、どのような成果が得られるのかを可視化して評価軸を考えるべき。医療を全国一律の法律で規制するのではなく、自治体の状況に応じて弾力的に運用できるようにしてほしい」とコメントさせていただきました。
創立150周年という大学の節目のイベントに、すばらしい登壇者の方々とご一緒させていただく貴重な機会を頂戴し、誠にありがとうございました。
ぜひお読みください。